こんにちは、ハウジング山一です。
日本で家を建てる以上、私たちが避けて通れない課題のひとつが「地震対策」です。阪神淡路大震災や東日本大震災以降も、震度7クラスの大地震は繰り返し発生しており、それに伴う余震も3〜4クラスの規模で長期間続くことはめずらしくありません。
ただ、20〜30年前に比べると、建物の耐震性は大きく進化しています。
昔の家は、重い瓦が乗った屋根が基礎と柱を緊結する「ホールダウン金物」が使われていないものも多く、大きな揺れで2階が1階に崩れ落ち、命を落とすケースもありました。しかし、現在は、屋根の軽量化やホールダウン金物の設置が標準化され、このリスクはかなり軽減されています。
とはいえ、現代の地震の傾向を見ると「一度揺れれば終わり」という単純なものではありません。繰り返しの強い揺れに耐えるためには、単なる耐震等級を超えて「家全体のバランス」に注目する必要があるのです。
●平屋という選択肢

耐震性を高めるという観点からまず考えたいのが「建物の形態」です。2階建てと平屋の家を比べると、同じ間取り条件であれば、平屋の方が耐震性は高くなります。
なぜなら、2階建ては1階部分にリビングなどの大空間を設け、2階部分に個室を集めることが多くなるからです。この場合、2階は柱や壁が多く重くなるのに対して、それを支える1階は柱や壁が少なくなり、バランスが崩れやすいのです。
さらに、採光を確保するため1階に大きな窓を設置すると、耐震に必要な壁量が減少します。結果として、地震の力が加わったときにバランスを損ないやすい構造になってしまうというわけです。
そのため、可能であれば平屋を選択することが耐震面においては有利になります。特に中庭を備えた平屋なら、採光と耐震性を両立させることができる点でも優れています。
●耐震性で最も大事なのは「バランス」

構造計算や耐震等級の数値はもちろん大切ですが、そこで見落とされがちなのが「全体のバランス」です。人でたとえるなら健康維持において食事のバランスが大切だったり、運動と休養のバランスが必要だったりするのと同じです。
家づくりでも「南向きに大きく開けたい」「日射をしっかり取り込みたい」といった要望があります。もちろん採光は大事ですが、開口部を南に偏らせ過ぎれば耐震性は確実に低下します。南に大きな窓を設け、北側にはほとんど窓をつくらないとなれば、南北の壁量バランスが崩れるからです。
こうした偏りがある間取りは、見た目や快適性を優先した代償として、地震の揺れには弱くなってしまうのです。
したがって、耐震を考える際には「壁量をただ増やす」という発想ではなく、四方にバランスよく壁が配置されているか、上下階できちんと荷重を受けられているかを確認しながら設計することが欠かせません。
●中庭のある家は耐震に不利?
ときどき「中庭をつくると耐震性が落ちませんか?」という質問をお施主様からいただくことがあります。これは、半分正解で、半分誤解です。
確かに、中庭を設ければ内側の壁量は減ってしまいます。ただ、その代わりに中庭から十分な採光を得られるため、外周部に大きな窓を設けなくてもよくなります。すると、外周の壁を増やすことができ、結果として東西南北の四面にバランスよく壁を確保することが可能になるのです。
つまり、「中庭=耐震性が弱い」とは必ずしも言えません。設計次第ではむしろ耐震性を高めることさえ可能なのです。特に平屋と組み合わせれば上からの荷重の心配もなく、強風の影響も最小限に抑えることができます。耐震等級3を取得する際にも、中庭によって間取り制約を強く受けることは少ないのです。
●「数字」より「バランス」を意識する
もちろん、耐震等級や制震・免震といった性能を高める仕組みも重要です。しかしそれと同時に大切なのは「構造的にバランスが取れているか」という点です。
どれだけ高性能な構造部材や工法を採用しても、壁の配置や荷重の流れに偏りがあれば、その家は揺れに弱くなってしまいます。逆に、平屋や中庭住宅のように「壁を均等に配置し、荷重をバランスよく受け止める設計」ができていれば、数字以上に実際の安心感を生み出すことができるのです。
耐震の強さは「等級や性能の数字」で測ることが多いですが、同時に重要なのは「家全体のバランス」です。
・平屋は耐震性に有利
・窓や壁の配置が偏ると弱くなる
・中庭は採光面で外周壁を増やせ、むしろ耐震に有利になることもある
・単なる壁量ではなく「四方のバランス」を確保することが大切
こうした視点を意識しながら計画すれば、より強くより長持ちする住まいをつくることができます。地震大国・日本で安心して暮らすために、ぜひ「バランス」を意識した耐震計画を進めましょう。
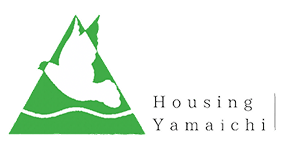

 お問い合わせ
お問い合わせ
 資料請求
資料請求